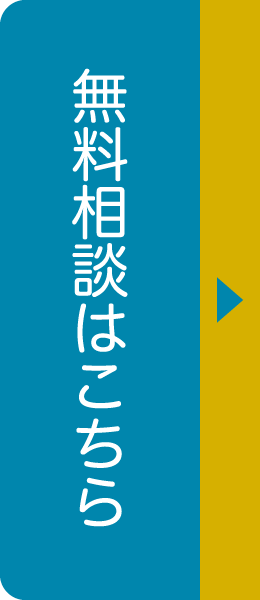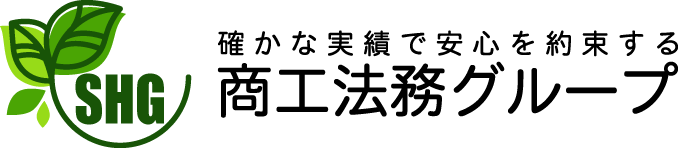住宅明渡しの強制執行は、裁判所の判決や決定に基づき、住み慣れた家から強制的に退去させられるという、人生において非常にマレな出来事です。裁判開始から強制執行、そしてその後の遺留品売却までの流れは、ほとんどの方にとって馴染みがなく、どうすれば良いのか途方に暮れてしまうでしょう。「まさか自分が…」そう思ってしまうかもしれません。
30年以上、累計3500件以上の強制執行の現場に立ち会ってきた執行補助業者として、明渡を求められた債務者の方々が、各段階でどのように行動すべきか、経験に基づいた生の情報と共にお伝えします。少しでもあなたの不安を解消し、取るべき行動を明確にするお手伝いができれば幸いです。
1. 裁判の開始と訴状の受領:「見て見ぬふり」は絶対にNG!
- 裁判所からの通知: 債権者(大家さんや金融機関など)が住宅の明渡しを求めて裁判所に訴訟を提起すると、裁判所から債務者であるあなたに対して、訴状や呼出状などの重要な書類が「特別送達」という形で郵送されてきます。「そんな書類、受け取っていない」という方も少なくありませんでしたが、郵便受けには必ず不在通知が入っていたはずです。「見ていない」「知らなかった」では、裁判所では一切通用しません。
- 債務者としてすべきこと: まず、訴状は絶対に放置しないでください! あなたの言い分を主張する機会を自ら放棄することになります。内容をしっかりと確認し、書かれている期日や内容を把握しましょう。そして、できる限り早く弁護士や弁護士会などの無料法律相談窓口などを活用して、今後の対応について法的アドバイスをもらうことを強くお勧めします。ご自身の状況を客観的に把握し、取るべき対応を検討するためにも、専門家の意見を聞くことが何よりも大切です。
2. 裁判の進行と対応:「和解」が最後の砦となる可能性も
- 裁判期日の出廷: 裁判所から指定された期日には、原則として必ず出廷する必要があります。これは、裁判官に対して、あなたの状況や言い分を直接主張できる貴重な機会です。やむを得ない理由で出廷できない場合は、事前に裁判所に必ず連絡し、指示を仰ぎましょう。中には、陳述書(書面での主張)を提出して済ませようとする方もいらっしゃいますが、経験上、特に家賃滞納による明渡裁判においては、あまり有効ではありません。また、ご自身が出席しなければ、債権者との和解交渉を進めることは絶対にできません。
- 債務者としてすべきこと: 裁判官から和解や調停の提案があった場合は、債権者側が拒否することもありますが、そうでない場合は積極的に検討しましょう。裁判官が中立な立場で間に入ってくれることで、あなたの意向を踏まえた、より現実的な条件で合意を目指せる可能性があります。相手方にもよりますが、この段階が強制執行を回避するための最後の、そして最大のチャンスとなる可能性が高いことを、強く覚えておいてください。
3. 判決または和解の成立:「約束」は必ず守る
- 裁判の結果、債務者であるあなたに対して不動産の明渡しを命じる判決が出されることがあります。また、裁判所の仲介による和解で、明渡しについて合意することもあります。
- 債務者としてすべきこと: 判決の場合は、判決書の内容を隅々までしっかりと確認し、定められた明渡し期限を正確に理解することが最も重要です。和解が成立した場合は、和解条項の内容を再度きちんと確認し、必ずその内容を遵守してください。判決であれ和解であれ、定められた期限までに自主的に明け渡す準備を始める必要があります。すぐに転居先を探し始め、引越し業者を手配するなど、具体的な行動を先延ばしにせず、今すぐ始めましょう。和解条項を破ったり、判決で定められた期限までに自主的な明け渡しが難しい場合は、残念ながら強制執行の手続きが確実に進められることになります。
4. 強制執行の申立て(申立):「執行文」に注意
- 債務者が判決などで定められた期日までに自主的に不動産を明け渡さない場合、債権者は裁判所に対して強制執行の申立てを行います。それに先だって、債権者が裁判所に「執行文付与申立」を行った場合、債務者であるあなたにも裁判所から通知が届きます。しかし、裁判での和解時や判決時に、既に執行文が付与されている場合は、この段階であなたに何の連絡もないこともあります。債権者の了解を得ている案件では、私はこの時点で任意に現地調査を行い、債務者の方と面談できる際には面談して、強制執行が申し立てられたことを直接お伝えするようにしています。債権者にとっても債務者にとっても、その方が事態が円滑に進むことが多いからです。ただし、このようなケースは一般的ではありませんので、「連絡がないから大丈夫」と安易に考えるのは危険です。
- 債務者としてすべきこと: 執行文付与申立の通知が届けば、強制執行が本当に差し迫っていることを強く認識してください。何も連絡がない場合でも、判決や和解で定められた期限を過ぎれば、いつ強制執行が申し立てられてもおかしくない状況であることを理解しておきましょう。引き続き、弁護士などの専門家と緊密に連携を取り、今後の具体的な対応について、再度相談してください。
5. 強制執行開始と債務者への通知:「催告」に向けて準備
- 強制執行の申立てが裁判所に受理されると、債権者は裁判所の執行官と、実際に明け渡しを行う前に行われる「催告」の期日の打ち合わせを始めます。執行官によっては、この打ち合わせの際に、さらにその先の「断行」期日(いわゆる強制執行の本番)の打ち合わせまで済ませてしまうこともあります。
6. 執行官による催告:「突然の訪問」に備える
- 強制執行の申立て後、実際に明け渡しを行う「断行」の前に、執行官が不動産の状況や明け渡しの見込みなどを調査し、債務者に任意の明渡を「催告」する作業が行われます。裁判所によっては、事前に「催告」を行う日時を債務者に通知するところもありますが、ほとんどの裁判所では、債務者に通知することなく、予告なしに「催告」が行われます。そのため、この時点で初めて、ご自身が強制執行という非常に厳しい状況に置かれていることを知るケースが非常に多いのが現状です。
- 債務者としてすべきこと: 執行官が予告なしに自宅にやって来ると、不在の場合でも鍵を解錠して室内に立ち入られ、「公示書」という書面が室内に貼り付けられ、「催告書」が目立つ場所に置かれます。もし在宅時に執行官がやってきたならば、可能な限り立ち会い、誠実に対応しましょう。執行官の権限としては、「催告」の当日であっても、法的には「断行」を行って、あなたを部屋から追い出してしまうことも可能です。自主的な明け渡しの意思を明確に伝えることが、その場で可能な唯一の、そして最も重要な対応策となることもあります。また、債権者によっては、この段階で滞納分を一括で支払うことを条件に明渡を猶予してくれる場合もありますが、残念ながらあまり期待しない方が良いでしょう。「催告」から「断行」までは、通常、最長でも1か月以内と非常に短い期間です。もし急いで引っ越し先を探す必要があるならば、最低でも3週間は必要ですので、一刻も早く行動を開始しましょう。引っ越し費用がないといった場合は、決して諦めずに、自治体の福祉窓口などで相談し、各種の福祉制度(生活保護など)を利用する方法がないか、すぐに確認してください。
7. 明け渡しの断行(立ち会い必須):「その日」を迎える前にできること
- 明け渡しの催告書の期限が過ぎても債務者が自主的に明け渡さない場合、いよいよ強制的な明け渡しである「断行」が行われます。もしそれまでに引っ越すことができなかった場合は、断行期日には原則として必ず立ち会ってください。
- 債務者としてすべきこと: 断行当日までに、現金や通帳などの貴重品、そして個人的に特に重要な思い出の品などは、必ず事前に自分で運び出すか、まとめて分かりやすいように分別しておきましょう。断行当日は、執行官の指示に冷静に従い、搬出作業にできる限り協力してください。全ての家財道具が搬出された後(場合によっては、荷物を運び出さずに、現地で梱包だけを行い、後日改めて搬出する「現場保管」という方法が取られることもあります)、執行官が不動産の明け渡しが完了したことを確認します。
8. 遺留品の保管と目録作成:「最後の砦」を無駄にしない
- 断行時に不動産内に残された家財道具(遺留品)は、一旦債権者または執行官が指定する倉庫などに保管されます。この際、執行官が遺留品の目録を作成します。保管された遺留品は、一定期間内(通常は2~3週間程度)に、債務者が引き取ることができます。この期限と遺留品の保管場所については、断行時に執行官から通知されます。もし断行に立ち会わなかった場合は、後日、ご自身で裁判所に問い合わせるしかありません。この引き取り期限を過ぎてしまうと、遺留品は執行官によって競売などの方法で売却されてしまいます。
- 債務者としてすべきこと: 通知された期限内に、可能な限り遺留品を引き取るようにしてください。売却されてしまうと、二度と手元に戻らない可能性が高いです。
強制執行を避けるために:「早期相談」と「誠実な対応」が鍵
裁判で明渡しを求められた場合、最も重要なのは、問題を放置せずに一刻も早く動き出すことです。弁護士などの専門家にできるだけ早く相談し、適切なアドバイスを求めたり、債権者との交渉や和解のサポートをしてもらったりすることが、強制執行を回避するための第一歩です。また、残念ながら強制執行に至ってしまった場合でも、執行官に対して誠実に対応し、指示に従うことで、手続きを円滑に進めることができます。
私たちのような執行補助業者は、債権者側から依頼を受けて仕事をしていますが、3500件以上の現場を見てきた経験から言えるのは、多くの場合、債務者の方が誠実に対応してくださるならば、債権者側も可能な範囲で誠意をもって対応しようとすることが多いということです。
例えば、私自身も立ち会った3500件あまりの強制執行のうち、ほぼ1割近い300人ほどの方の生活保護受給手続きをサポートしてきました。債務者の方が現実から目を背けず、私たちに耳を傾け、誠実に状況を話してくれなければ、そのお手伝いをすることすらできません。
明渡を求められたら、決して一人で悩まず、一刻も早く専門家に相談し、現実から目を背けずに誠実に対応すること。これが、最悪の事態を避けるために、最も重要で、そして今すぐあなたができる心構えであり、行動なのです。