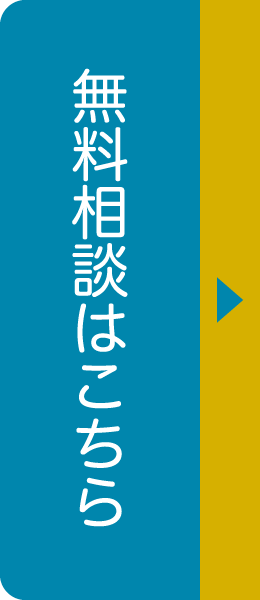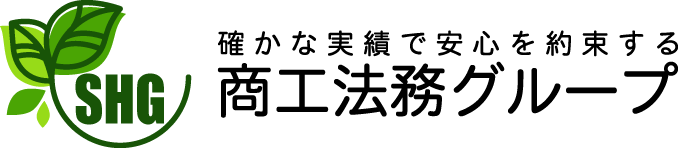最高裁判所事務総局民事局第三課執行・倒産手続係 調査員の藤原直人氏による分析記事が「事業再生と債権管理 190号」/金融財政事情研究会刊に掲載されており、その記事と全国競売評価ネットワークが公表した令和6年度(2024年1月〜12月、または司法年度)のデータをもとに、日本の不動産競売市場の最新動向の分析を紹介します。
全体として処理状況は良好に推移していますが、一部の指標には注視すべき変化が見られるようです。
1. 不動産競売事件の概況(全国)
令和6年度の不動産競売事件の件数は、新受・既済・未済のすべてで増加傾向にあります。特に新受事件数は微増傾向が続いています。
| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対前年比 | 備考 |
| 新受事件数 | 15,814件 | 17,559件 | 111.3% | 平成23年度以降の減少傾向から増加に転じる |
| 既済事件数 | 15,255件 | 15,360件 | – | 新受事件数を下回る |
| 未済事件数 | 11,322件 | 13,559件 | 119.8% | 新受と既済の差により増加 |
新受事件数は令和6年度に17,559件となり、対前年比で111.3%と増加しました。既済事件数が新受事件数を下回ったため、未済事件数は13,559件と増加しています。この未済事件数の増加は、今後もその動向を注視する必要があるとされています。
2. 処理期間の動向
競売手続の迅速性を示す「申立てから売却実施処分(1回目)までの期間」と「平均審理期間」についても微増が見られます。
申立てから売却実施処分までの期間 (1回目)
令和6年度の申立てから売却実施処分(1回目)までの期間は、全体的にわずかに延びています。
- 3か月以内の事件の割合は 5.9% (前年度9.4%)。
- 6か月以内の事件の割合は 69.1% (前年度74.1%)。
期間が延びた要因として、未済事件数の増加が一因として考えられます。ただし、執行官と評価人の連携による現況調査報告書・評価書の早期提出など、各執行裁判所の取り組みにより、処理に大きな問題が生じている状況ではないと評価されています。
平均審理期間
「申立てから終局まで」の平均審理期間は、令和5年度の平均8.4か月から、令和6年度は平均8.6か月へと微増しました。これは、令和5年度が平成22年以降で最も短い期間であったことからすると、安定した事務処理が行われていることを示唆しています。
3. 売却率と乖離率(高落札率の地域に注目)
不動産競売が適切に機能しているかを測る重要な指標である売却率と、物件が高値で売却されたかを示す乖離率(買増率=売却基準価額の何倍で入札されたかの割合)の動向は以下の通りです。
全国売却率の推移
令和6年度の全国の売却率(期間入札および特別売却)は77.3%でした。前年度より減少したものの、比較的高い水準を維持しています。
| 年度 | 売却率 |
| 令和2年度 | 80.7% |
| 令和3年度 | 83.4% |
| 令和4年度 | 83.6% |
| 令和5年度 | 80.7% |
| 令和6年度 | 76.9% (データソースにより77.3%の記載もあり) |
全国的に売却率は前年度と比較して低下傾向にあります。特に地方や地裁本庁に比べて支部での売却率が低い傾向が続いており、今後の課題とされています。
地域別売却率と高落札率の地域
地域別に見ると、大都市圏で特に高い売却率が維持されています。
| 高裁管内 | 令和6年度売却率 | 前年度比増減 (pt) |
| 東京高裁管内 | 86.0% | -3.7 |
| 大阪高裁管内 | 82.4% | -3.6 |
| 名古屋高裁管内 | 74.7% | -5.7 |
| 広島高裁管内 | 60.2% | -7.7 |
| 福岡高裁管内 | 74.3% | -2.9 |
特に、東京地裁本庁は99.4%、大阪地裁本庁は91.1%と、極めて高い数値を示しており、不動産競売市場の中心的な役割を担っています。
4. 乖離率(買増率)の動向と地域差
乖離率(買増率)は、落札金額を売却基準価額で除したもの(落札金額 ÷ 売却基準価額 売却基準価額の何倍で入札されたかの割合)で、競売市場における物件の評価水準を示す指標です。債権者にとっては、この数値が高いほど債権回収の目的達成につながります。
| 地域 | 令和6年度 乖離率 (全種別) |
| 全国 | 155.5% |
| 大阪高裁管内 | 175.4% |
| 福岡高裁管内 | 164.3% |
| 東京高裁管内 | 151.1% |
| 広島高裁管内 | 144.2% |
| 札幌高裁管内 | 147.0% |
| 名古屋高裁管内 | 141.4% |
| 仙台高裁管内 | 139.2% |
| 高松高裁管内 | 136.4% |
全国集計では、令和6年度の買増率は155.5%であり、前年度(令和5年度は153.2%)と比較して微増しています。
特に注目すべきは、大阪高裁管内が175.4%と全国で最も高い乖離率を記録している点です。これは、都市部(特に大都市部)では、一般市場価格と同程度か、それを上回る価額で売却されている物件が相当数あると考えられることを示唆しています。この高乖離率の背景には、執行裁判所が評価人候補者と協議し、競売市場修正率の変更の要否や範囲を検討していることが影響している可能性もあります。
5. 売却率向上のための取り組み
裁判所は、売却率向上と物件の高値処分を実現するため、インターネット上で不動産競売物件情報サイト(通称「BIT」)を運営しています。
BITでは、競売物件情報、売却結果、スケジュール、手続案内に加え、「3点セット(物件明細書、現況調査報告書、評価書)」の閲覧・ダウンロードが可能となっており、買受希望者が自宅などから質の高い情報を入手できる環境が整備されています。令和6年度には、トップページへのアクセス件数が月約60万件、3点セットのダウンロード件数が月約47万件と、広く定着しています。
まとめ
令和6年度の不動産競売事件の処理はおおむね良好な状況を維持していますが、新受・未済事件数の増加に伴い、処理期間の微増が見られました。売却率と乖離率は全国的に高い水準を保ち、特に東京地裁や大阪地裁などの大都市圏では極めて高い落札率・高額処分が実現しています。もちろんその物件にもよりますが、入落札を本気で検討するのであれば、平均的には売却基準価額の1.6倍以上での入札が必要となってくると考えたほうがいいかもしれません
。