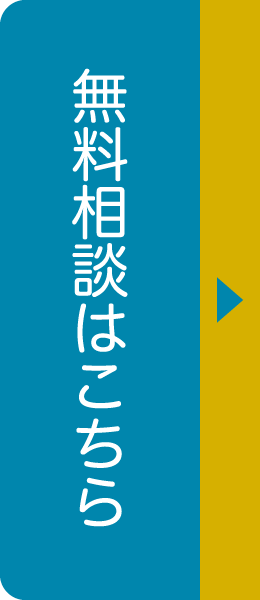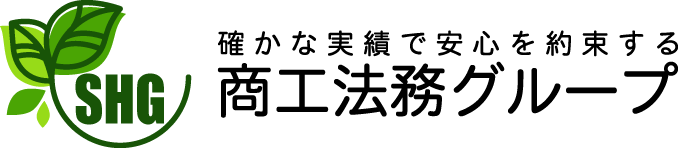当センターが行っている高齢者向けの身元保証サービス事業は、厚生労働省による定義づけでは「身寄りなし」高齢者支援事業となります。現在は、ガイドラインだけが定められていますが、法律的な制限や制度設計があるわけではなく、例えるならば、「無法地帯」的な状況といえます。この状況を改善しようと、厚生労働省なども動き出しています
1. 事業の目的と位置づけ
- 目的: 頼れる親族などがいない「身寄りなし」の高齢者が、経済状況にかかわらず、地域で安心して生活し、最期を迎えられるよう支援すること。
- 法的位置づけ:社会福祉法を改正し、これらの身元保証サービスや高齢者の支援事業を「第2種社会福祉事業」に位置づける方針です。第2種社会福祉事業とすることで、必要な手続きを経て、社会福祉法人やNPO法人など、幅広い主体が事業に参入できるようになります。
2. 提供される具体的なサービス内容
この新事業で想定されている支援は、主に高齢者が抱える生活上・終末期の「困りごと」をワンストップで解決するものです。
| 支援分野 | 具体的なサービス内容(想定) |
| 生活支援・金銭管理 | 日常生活における金銭管理、公共料金や家賃などの支払い代行。 |
| 入院・入所支援 | 病院への入院、介護施設への入所・退所に関する手続き代行、緊急時の連絡先・身元引受機能の一部代替。 |
| 療養に関する意思決定支援 | 延命治療などに関する本人の意思確認・意思表明の支援。 |
| 死後事務支援 | 葬儀・火葬・納骨の手配、行政手続き(死亡届の提出など)、未払い費用の精算、残された家財・遺品の整理。 |
3. 対象者と利用形態
- 対象者: 主に、経済的な理由や人間関係の希薄化などにより、高額な民間の身元保証サービスを利用することが難しい「身寄りなし」の高齢者が想定されています。全国展開している身元保証サービス事業者の必要費用は、おおむね100~200万円ほど必要なところが多いようです。当センターのように33万円でOKというところは、あまりありません。それらの費用が支払えない方向けの貧困層がターゲットだとすると、中間層の方々はどうするのかという問題は残ります。
- モデル事業: この新制度の創設に先立ち、政府は2024年度から、公的機関が主体となった同様の支援を行うモデル事業を全国の市区町村で実施し、具体的な運用方法や課題を検証しています。いまのところ判明しているのか、下記の地域です。
| エリア | 都道府県・市区町村名 | 実施メニューの傾向 | 備考 |
| 東北 | 青森県弘前市 | パッケージ支援 | 令和7年5月開始 |
| 福島県伊達市 | 相談窓口 | 令和7年6月開始 | |
| 関東 | 茨城県東海村(予定) | パッケージ支援 | 令和7年10月開始予定 |
| 千葉県我孫子市 | パッケージ支援 | 令和7年4月開始 | |
| 千葉県船橋市(予定) | パッケージ支援 | 開始予定 | |
| 東京都文京区 | パッケージ支援 | 令和6年4月開始(早期事例) | |
| 東京都品川区 | パッケージ支援 | 令和7年4月開始 | |
| 神奈川県川崎市 | パッケージ支援 | 令和6年4月開始(早期事例) | |
| 神奈川県大和市 | 相談窓口 | 令和7年4月開始 | |
| 中部 | 山梨県甲府市 | 相談窓口 | 令和7年4月開始 |
| 静岡県静岡市 | 相談窓口 | 令和7年4月開始 | |
| 愛知県岡崎市 | 相談窓口 | 令和6年7月開始 | |
| 愛知県豊田市 | 相談窓口・パッケージ支援 | 令和6年10月(相談窓口) | |
| 近畿 | 京都府京都市 | パッケージ支援 | 令和6年4月開始(早期事例) |
| 大阪府枚方市 | パッケージ支援 | 令和6年10月開始 | |
| 九州 | 福岡県福岡市 | パッケージ支援 | 令和6年4月開始(早期事例) |
| 福岡県北九州市(予定) | パッケージ支援 | 令和7年10月開始予定 |
令和6年度(2024年度)の早い時期から開始している自治体(東京都文京区、神奈川県川崎市、京都府京都市、福岡県福岡市など)なども、この公的支援の取り組みの先駆的な事例として注目されています。
4. 今後の見通し
- 法改正の時期: 厚生労働省は、この新事業の創設に向けた社会福祉法などの関連法改正案を、来年(2026年)の通常国会に提出することを目指しています。
- 意義: この公的支援の枠組みが整うことで、身元保証サービスの「無法地帯」的な状況を改善し、民間サービスを補完するセーフティネットとして機能することが期待されています。
ただ、どちらかというと貧困層の単身高齢者をターゲットにしており、中間層への目配りが少ないように感じます。
当ねりま終活身元保証センターのような中間層向けに手軽な費用で、サービスを受けられるところはまだまだ少ないのが現実です。当センターの特徴は
- 預託金、保証金、遺贈は一切不要
- 初期費用は、すべて最初に行う遺言作成や死後事務委任契約、エンディングノート、見守りサービスの設定などの文書作成&見守などの設定費用のみ
- 死後事務や遺言執行は残された遺産から、できる範囲を相場の費用(おおむね5%)で
- センターのみならず、独立自営の行政書士などの士業者が連帯するので、サービスの破綻がおきにくい仕組み(万が一、センターがなくなっても費用等はおあずかりしていないので「預けた費用を失ってしまう」というリスクはありません。また、もしものときの死後事務や遺言執行は、担当の独立自営の担当士業者が最後まで行います。逆に担当士業者が職務不能になっても、かわりの士業者が担当する仕組みができています)。
- デメリットは、それらの仕組みが、お互い顔が見える士業者ネットワークを基本に作り上げているため、事業範囲を広げるのが難しいことです。なので、現在は練馬区および近隣市区町村のみを対象にしています。